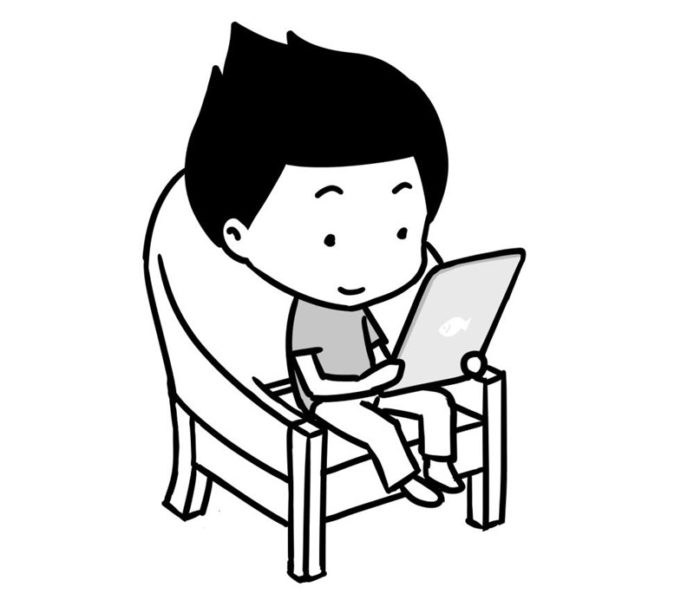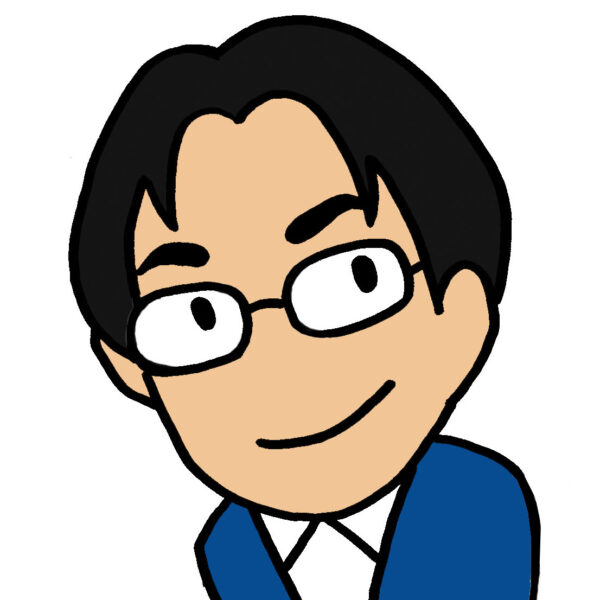高階良子『70年目の告白~毒とペン~』が完結した。さっそく読了した。
高階良子『70年目の告白~毒とペン~』が完結した。さっそく読了した。
私は高階良子さんという作家が、漫画家のなかではもしかするといちばん好きかもしれない。知っている限り全作品を読んでいるはずだ。「ピアノソナタ殺人事件」や「赤い沼」「マジシャン」などは連載中にも読み、単行本でも読み、電子書籍も買っている。そういう意味では手塚治虫さんよりも好きかもしれない。
自分が小学生だったころから、この作家さんのお母さんはそうとうにキビシイ人なのだろうと想像はしていた。作品の多くに、随所に、そういう感触を伝えてくるものがあった。私は小学校のころからいわゆる「カウンセリングもの」が好きで、河合隼雄さんの簡単なものはいくつか読んでいた。
しかしこの『70年目の告白~毒とペン~』を読んでなんともいいようのない気持ちにさせられた。「キビシイ」とはこの場合には適切ではない。「狂気」としかいいようがないレベルだった。あの状況で、あれほど多くの「高階作品」を出し続けてこられるものだろうかと不可解な印象が残った。
けれども本作のとくに第3巻を読んで、たぶん著者が意図しない効果を私は感じずにはいられなかった。この狂気の母親に私は同情のあまり泣いてしまったのだ。あまりに不幸な人だと思った。
「中年の危機」にぶつかってから乗り越えるまで
私だったら娘が大成功して、大金持ちになって、家まで用意してくれるようだったら、ムスメを太陽神よろしく諸手を挙げて拝まずにはいられなくなるだろう。
記事を書く前にはいくつか引用したい箇所があった。けれどもいまこうして書いているとぜんぜん引用する気がしない。それくらい「いいお母さんのシーン」がないのだ。ひとつもない。
本作のなかで高階さんが何作もヒットを飛ばしている。私はそのすべてを知っている。中学、高校と、私のレベルをはるかに超えた「進学校」の、定期試験の苦しみにぶつかるたび、「地獄でメスが光る」「魔界樹」「昆虫の家」などを徹夜で読んだのを思い出した。
そんな大作家が母親に罵声を浴びせられ、金を勝手に管理され、殴られ、それに耐えながら「このままじゃいつか気が狂う」などとモノローグしている。
こうした天才的な人が「発狂の恐怖」に耐えながら仕事していると、不思議なことに「精神分析」が始まる。それが数ページおきにふと現れる。それが高階良子を狂気から救って新しい作品を生み出させた。私にはそういうふうに読めた。
ただしそんなことは高階良子だからできたのであって私にはムリだ。だから私たちには「カウンセリング」というものが必要なのである。あんな中で自力でがんばっていたらほんとうに気が狂ってしまう。私ならあのはるか手前の苦しみにもまったく耐えがたい。そこで倉園佳三さんなどのセッションを受けさせてもらうのである。こういうのは必要なことだ。
私たちの多くは相互にカウンセリングしなければいけない人間である。東畑開人さんの「聞いてもらう技術」がこんなにヒットしているのはそういうことだと思う。
私自身は45歳ころからジワジワと「中年の危機」にぶつかっておかしくなりそうだった。それでも、小学校のころから河合隼雄さんを読んでいたのに、ついに「心療内科」にも「カウンセリング」にも通う選択ができなかった。
世には臨床心理士があふれるほど(?)いるといわれているのに、なにかがうまくかみ合っていない。夫婦の不仲やレポートの締め切りなど、凡庸な日常の、ありきたりな悩み事でも、ときどき胃がよじれそうになるほど人を苦しめることはある。
それなのに、頼れる専門家が世にあふれていると言われるなか、私たちはその種の苦悩に自力で立ち向かおうとしがちである。
どんな悩み事であれば堂々と「専門家」を頼ることができるのだろう?
そもそもその専門家にまず「なにをどのように」伝えればいいのだろう?
私の人生なんかは恵まれているはずだが、それでも定期的に「危機」が訪れる。
中学生のころなどはひどいものだった。しかし最終的には「自力」を頼りにした。頼りにまったくならない「自力」を「セルフ・カウンセラー」に支えてもらうかたちで、切り抜けるよりしかたがなかった。
「高階作品」はそうした「セルフ・カウンセラー」のひとつだったのだと思う。