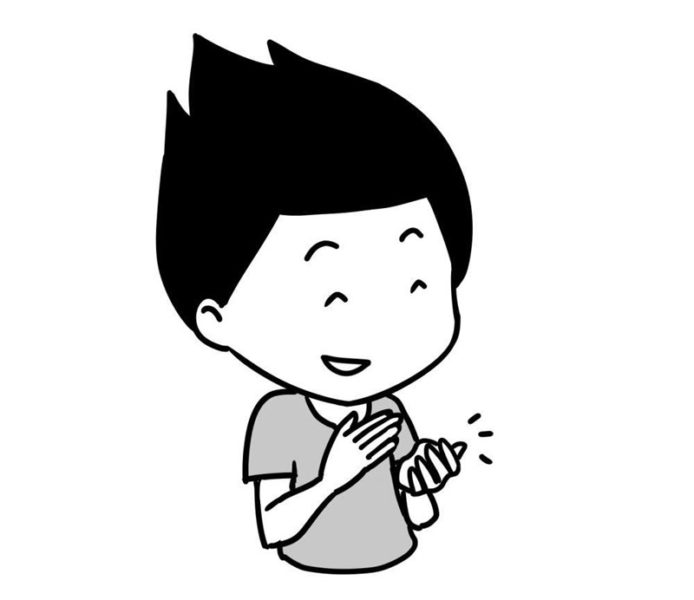今回は010を。デジタルツール・ライティングの嚆矢とも言える一冊です。
今回は010を。デジタルツール・ライティングの嚆矢とも言える一冊です。
- 『ワープロ作文技術』(1993)
外しがたい本
本連載では、極力現在でも入手しやすい本を挙げようと心がけています。古典研究ではないのですから、やはり今、手にとりやすい書籍の方が親切でしょう。その点で言えば、本書は若干選択が難しくあります。おそらくは絶版でしょうし、電子書籍にもなっていません。
とは言え、「知的生産の技術書」というセレクトにおいて、特に「有用な知的生産の技術書」というセレクトにおいては本書を外すわけにはいきません。
なぜなら「ワープロを使った執筆のスタイル」という現代にも十分通じるノウハウが開示されているからです。
デジタルツール・ライティング
本書は1993年に出版されていますが、2022年の現代においても本書のノウハウと考え方は通用します。逆に言えば、さまざまデジタルツールが登場したものの「執筆のスタイル」はこの20年あまりでたいした変化はしなかったと言えるのかもしれません。むしろ、本書のような考え方を採用せず、「原稿用紙を使った執筆のスタイル」のままにデジタルツールを使っているむきもあるくらいです。
もちろん、知的生産作業では「頭を使う」作業が必要になり、そこには必然的に「身体化」された作業が含まれるので、慣れ親しんだ方法の方が効果があげやすい、という点はあるでしょう。それでも、慣れ親しんだ方法から一歩外に出てみる努力はいつだって有用ですし、せっかくデジタルツールを使うのだから、その良さを十全に発揮させようとするのも間違った試みではないでしょう。
その意味でも、ワープロ=デジタルツールを使った執筆作業が論じられている本書は議論の出発点でもあり、今でも使える有用なノウハウを提供してくれる希有な一冊でもあります。
書いて考える、書きながら考える
本書は「作文技術」と銘打たれていますが、構成の型や言葉遣いの方向性を提示してくれるような内容ではありません。そうではなく、「執筆作業はどのように進んでいくのか」というプロセスを提示・検討してくれる本です。本の「コンテンツ」について直接論じるのではなく、そのコンテンツがいかなるプロセスを経て生み出されていくのかが開示されているのです。
たとえば第1章「構想を立てる」では、いかなる構成の型がありどうそれに近づけていったらいいのか、という「具体的」なノウハウは語られておらず、その代わりに、人がどのように構成を作っていくのか、という「具体的」なノウハウが語られています。
たとえば〈太公望方式〉として、何かしらその企画について思いついたことがあればメモし、それを膨らませていくという手法が紹介されます。これは比較的短い文章で使える方法です。一方で、長い文章の場合はもう少し「組織だった」方法が必要です。著者はそれを魚群探知方式と名付けています。簡単に言えば、まず目次案を作り、それを見ながらあれやこれやと肉付けしていく方法です。一本筋の通った大きめの文章を書く場合は、こうした目次案を通した検討はかなり有効です。
とは言え、です。
そうやって最初に目次案を書いたらあとは No problem というわけにはいきません。
もっとも、目次案さえ適当に書いてしまえば、あとは各章の各節を順に言葉で埋めるだけでよい、原稿書きなどちょろいものじゃ、などと高を括ってはならない。世の中にはそう信じ込んでいる人が結構いるようだが、迷信というほかはない。
(前略)これが常態であって、目次案がそのままの形で最終原稿の目次として残るのは、むしろきわめて稀なことである。
つまり、最初に作る「目次案」はあくまで「こうなるかも、こうなったらいいな」というイメージであって、実際にできるものはそれとは違っていると言うのです。実際は、書きながら目次案というものは変わってくる。そういうプロセスが起こります。
たとえば、
- 章の順番が変わる
- 新しい章が追加される
- 既存の章が削除される
- 章の項目が入れ替わる
といったことが起こるのです。
なぜそうしたことが起こるのかは、また別の回で検討してみますが、実際に文章を書いたことがある人ならば一種の「あるある」話でしょう。当初のプロットや目次案から文章が「逸れて」しまうのです。
これがアナログツール≒原稿用紙ならば大惨事です。上記のような Happening が発生したらその帳尻合わせは悲惨な作業量になります。というか、まだ原稿用紙ならば並び替えができるのでマシなくらいです。綴じノートに書いていたら順番の入れ換え自体が不可能になってしまいます。
しかし、デジタルツールならばそうした帳尻合わせ=編集をやすやすとやってのけます。むしろ、そのためのツールだと言えるくらいです。この点は、009『「知」のソフトウェア』にも書きました。ツールによって容易に編集が可能になったことによって、新しいライティングのスタイルが可能になったのです。
つまり、とりあえず「あたり」をつけて書き始め、あとは書きながら考え、その考えを原稿=全体に反映させていく、というプロセスが現実的にとれるようになったわけです。
それは、執筆というプロセスを「トップダウン」だけで進める必要がなくなったことを意味します。一つの解放が訪れたのです。しかし、それはそれで別の問題をもたらしたわけですが、それもまた別の回で検討しましょう。
さいごに
『ワープロ作文技術』は、これ以外にも面白い話がわんさかありますので──多少入手は難しいですが──、図書館などで探してみてください。「ワープロ」というデジタルツールの可能性が現代でも十分に感じられると思います。
▼倉下忠憲:
新しい時代に向けて「知的生産」を見つめ直す。R-style主宰。メルマガ毎週月曜配信中。