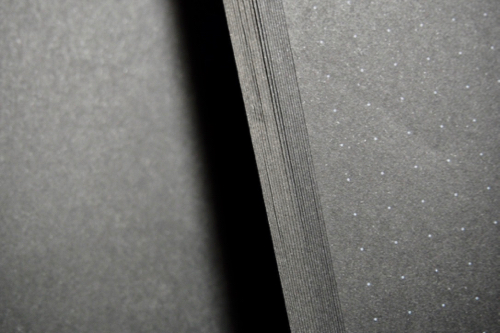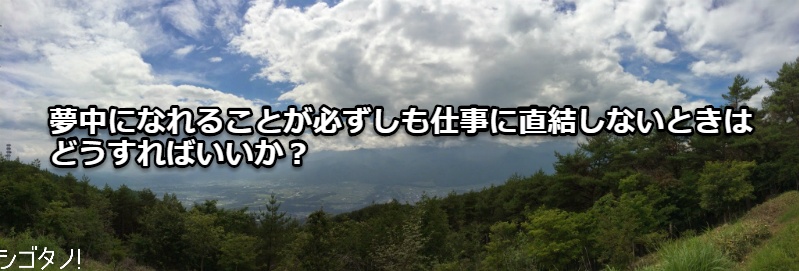
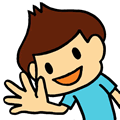 ここ最近は、タイトルに掲げた「夢中になれることが必ずしも仕事に直結しないときはどうすればいいか?」問題に頭を悩ませています。
ここ最近は、タイトルに掲げた「夢中になれることが必ずしも仕事に直結しないときはどうすればいいか?」問題に頭を悩ませています。
それは本来は自分がしなくてもいいことではありながらも、それをすることはまったくのムダとは言い切れないこと。
あえてそれが何であるかについてはハッキリとは書きませんが、ご自身の中で「それ」に当たることを思い浮かべながら読み進めていただければと思います。
時間があればあるだけ全部それにつぎ込んでしまう
こう書くと、何やら中毒や依存症のような様相を呈してきていますが、実際のところ何かに没頭していれば、他のことがいっさい目に入らなくなる、気にならなくなるわけですから似たようなものでしょう。
調べれば調べるほどに、理解が進めば進むほどに、ますますのめり込んでいく。
「なるほど、そういうことなのか。では、こういう場合はどうなるのだろう?」
などと、知れば知るほど芋づる式に新たに知りたいことが次々と湧いてくる、底なし沼のような「たこつぼ」なのです。
対策は1つだけ
「こんなことをしている場合ではない!」という正気を保つ自分に後ろ髪を引かれつつも、「いや、もうちょっと、これについて調べたら終わりにするから」と不敵な笑みを浮かべつつその場を動こうとしない狂気に触れた自分との果てることのない綱引き。
「こんなことをしている場合ではない」以上、時間を吸い取り続けるこの貪欲な“蛭(ひる)”をどうにかして引きはがしにかかる自分が一方で、「吸わせておけ!」と吹っ切れている自分もまた健在なのです。
対策としては、とことん突き進み、最大の力を振り絞って「底」に迫ること。
その際に、記録を欠かさないこと。
狂気に駆られつつも、“記録脳”だけは冷静さを保ちつつ、起きていることをつぶさに観察し、これを記録に残していくこと。
もしここで記録するのが煩わしく感じるとしたら、それはその程度のものだと割り切り、振り切ることが容易にできるでしょう。
逆に、「これは記録に残して、後からじっくりと検証したい」あるいは「そう遠くない未来にこの世界に足を踏み入れてくるであろう人たちのための手引きを残したい」といった、ここまでクリアに言語化しなかったとしても、とにかく到底そのままにしておくわけにはいかないという謎の高揚感と使命感に駆られる感覚です。
ここで思い出すのは『人蕩術極意』(人蕩術シリーズ3部作のうちの2作目)に出てきた以下のエピソード。雰囲気を伝えたいので、長めに引用します。
ある秋のウィーク・デイに、上高地から西穂高方面へ登山したことがあります。
西穂高はもう何回か登っているので、この日は、そこまで登る気はなく、その途中にある独標(どっぴょう)まで、ぶらぶら行ってみようと思ったのです。
天気の良い日で、独標の近くの岩峰に立った時、はるか下方に大正池とあずさ川が見えました。太陽は正午近かったので、中天に輝いており、すべてが眩しく、暖かでした。
私は腰をおろし、水を水筒から少し飲み、チョコレートを一片、口の中に放り込みました。それは甘く、ゆっくりと舌の上で溶けていきました。
空を見ると、雲が文字どおり湧き、踊り、走り、消え去っていきます。遠い川筋は、白い銀のように陽光を反射しておりました。
ふと、左手のはい松の向う側に、雷鳥がいるのを見つけました。ニワトリほどの大きさの灰色のその鳥は、こちらをじっと見ているようでした。
私は思わず、にっこりと笑いかけました。しばらくすると、雷鳥の姿は、はい松の向うに隠れてしまい、どこかへ行ってしまいました。
太陽はゆっくりと蒼天を西に移動しつつあり、雲は湧いては消え去り、時間は気がつかないうちに大分過ぎ去りました。北アルプスの山々は、少し影を増してきたようです。
今、思うに、この時の私は、完全に一人ぽっちでしたが、孤独感や淋しさはありませんでした。沈黙はしていましたが、陽気さは心に満ちており、何か生き生きとした力が身内に感じられました。
突然、この時に、何か胸の内から、のどにかけて、熱いものが吹き上げてきたのです。そして、世界中が、いきなり「ワーッ」と燃え立ったように感じられたのです。
この時の感じは、どうもうまく表現できないのです。強いていうと、どうも性的な喜びとも似ていたようでもあり、また、「自分はなんと運がいいんだろう」といった感謝のような気分でもあったようです。
ただ、言葉で「ありがたい」とか「うれしい」とかいったような白けたようなものでなく、身もだえするようなエクスタシー的なものでした。
例えようのないこの歓喜の感覚は三十秒ほど続いたでしょうか、次第に静まり、私の感情は落ちつきを取り戻しました。
しかし、この後、下山してバスに乗る頃まで、何回も、ワクワクするような嬉しさの思いが、胸もとに突き上げてくるのを感じたのです。
何年か過ぎて、私はあれが「絶頂体験」というものであることを知り、禅でいう「覚醒」に近い経験であることを知りました。そして、その頃から、人々は私の顔つきがすっかり変わってしまったといってくれるようになりました。
かかる「絶頂体験」には遠く及びませんが(比較できないために及ぶかどうかすら判断がつきませんが)、折に触れてこのくだりを思い出すたびに、ここに少しでも近づくためには何が必要なのか、あるいは何が不要なのか、を考えるようになりました。
その1つが、今回書いた、とことん突き進み、最大の力を振り絞って「底」に迫ること、ではないかと予感しています。