
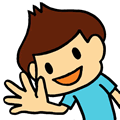 文章を書くとき、特にこのブログの記事を書くときは、事前に構成を考え、検討を重ね、盛り込む事例もこの段階で出し切り、「よし、これならいける!」という手応えを得てから書き始めるようにしています。逆に言えば、手応えが得られない限り書き始められないので、常に複数の構成案が滞留してしまいます。今回はこの問題について考えてみます。
文章を書くとき、特にこのブログの記事を書くときは、事前に構成を考え、検討を重ね、盛り込む事例もこの段階で出し切り、「よし、これならいける!」という手応えを得てから書き始めるようにしています。逆に言えば、手応えが得られない限り書き始められないので、常に複数の構成案が滞留してしまいます。今回はこの問題について考えてみます。
この問題を解決するための突破口となっているのが『いますぐ書け、の文章法』という本。
特に以下の一文は僕にとっては「天啓」でした。
書く前に考えたことしか書けない文章は失敗である。
書く前に完全な見通しは立たない
「書く前に考えたことしか書けない文章は失敗である」の意味するところは以下の通り。
書いている最中に、新たなアイデアが浮かんでくる。逃がさないようにして、いま書いている文章に取り込む。その繰り返しである。
書いているから、新たなアイデアが浮かんでくるのである。
書いてる最中に何も新しいことが浮かんでこなければ、それは失敗だ。
書きたくない内容なのに書いているから、そうなる。それは失敗である。(p.149)
特に最後の一文は突き刺さります。好きで書いているのに、伝えたいと思って書いているのに、実は「書きたくない」と思っていることにされてしまっては心外というものです。
でも、いざ書き始めてから立ち往生するようなことは避けたいので、書く前に可能な限り完全な見通しを持って出発することになり、この姿勢は「書いている最中に浮かぶであろう新しいアイデア」を受け入れる姿勢とは相容れません。
すべてを予定通りに進行させたいが、割り込みも積極的に受け入れたい、という良く言えばフレキシブルですが、要するに「都合の良いことを言っているだけ」だからです。
文章の自走に任せる
ところで、著者の文章に対する考え方に、ハッとさせられました。
以下のくだりです。
事前に書くと決めたことだけを、きちんと書きたい。書いてる最中に湧いてくる余計な想念に惑わされたくない、と考える人もいるだろう。
でも私から見れば、それは、あまり文章を書く人には向いてない。文章を書く醍醐味は、文章の自走に任せるところにある。そういう文章は「書き手であったはずの自分」さえも「読み手として驚かせる」ことができるのだ。
それが文章の持っているもっとも強い力のひとつだとおもう。(p.161)
特に「文章の自走に任せる」という一文を目にしたときに「そうできるならば是非そのようにしたいが、それで本当にうまくいくのか?」という強い疑念が自分の中に根づいていることに気づきました。
同時に、自分なりに「うまく書けた!」と思えたときは、まさに「文章の自走に任せ」たときだったではないか、という実感も確かにあります。
そして、
あとで読んで、これ、おれが書いたのか、よくこんな表現をおもいつくよな、とおもえるとすごく楽しい。
日常生活で使ってる頭の部分で見ると、よく知らない人が書いてるものに見える。それが、書いていて、おれにとって、いい文章。(p.159)
という部分はまさに思い当たるふしが大いにあり、「確かに!」と心の中で叫びながら読みました。
過去に書いた記事を読み返しながら、著者と同じく、我ながら「よくこんな表現をおもいつくよな」と思ったことは一度や二度ではありませんので。
とにかく、書くしかないのだ
WorkFlowy上で構成案を完全に作り切ってしまい、それをテキストエディタにペタッと貼り付けて、あとは機械的な整形作業をチョチョッとやればハイ完成、という感じにしたい。
そんな絵に描いたような美しく効率のよい文章作成フローはいったん忘れる必要があるということです。
ひとたび自分なりの「フロー」を組み上げてしまえば、その後は文章をどんどん量産できるようになるという構想があったわけですが、それは幻想だったわけです。
書き始める前に構成案を作り切りたいと考えるのは、事前に、見えている限りのハズレくじを全て取り除き切ってしまいたい、ということです。
でも、どれがハズレなのかは実ははっきりしていません。ハズレくじと思って取り除いたものが実は「当たり」だったことが後からわかることもあります。
「これは使えない」と切り捨てた素材が、後になって「文脈が変わったので、やっぱり使える!」と返り咲くことはザラにあります。
書き始めてみて初めてわかるのです。
だから、書くしかないのだ。
つまり、私の説明してることを、あなたも実際に体験してみるしか、文章をうまく書ける方法はない、ということだ。
だから、とにかく書け、なのだ。理屈を学んでる手間で書け、ということ。(p.166)
ここまで書いて、そういえば似たようなことを書いていたことを思い出しました(まさに、書く前は忘れていたことです!)。
とにかく始めることが最善だ、というのは頭では理解できます。
でも、
- 本当に今なのか?
- もっと良いタイミングがあるのではないか?
- あるいは別のもっとラクな方法があるのではないか?
などなど、考え始めるとキリがない。
決められない。
苦しい…。
どうすればいい?
この問いに対する答えは、「書くこと」でした。
自走する文章を書くには?
とはいえ、やっぱり知りたいですよね、「どうすれば、自走する文章が書けるのか」を。
著者はこんなヒントを用意してくれています。
自走する文章を書くには、「誰に向かって、どういうことを書いているか」が意識されているときだけ、である。(p.174)
文章それ自体が“使命”をハッキリと自覚したとき、文章は自ら走り始めるわけです。
映画の主人公のようです。
書く前に完全な見通しを立てることは、文章にいっさいの自由を与えずに、完全に支配下に置くことを意味します。アドリブをいっさい許さない、脚本通りの演技を強要するようなものです。
演じる自由を奪われれば、そりゃ、役者たる文章だって楽しくないし、監督たる書いているほうも面白くないわけです。
監督で思い出した
映画の喩えを持ち出してきたところで、ふと思い出したインタビュー記事があります。
Evernoteにクリップして、折に触れて目にしていたこともあり、「あ、あの記事だ!」とすぐに引き当たりました。
さっそくそのインタビュー記事を引用しようとしたら、すでに過去にも同記事を引用して記事を書いていることに気づきました。
シリーズドラマを観ていてうすうす感じていたことですが、すべてのエピソードについて、それぞれの各シーン一つひとつを事前に詳細に脚本上で計画し尽くすわけではないでしょう。
ある程度見えてきたところで「よっしゃ、これで撮影にはいろう」となるはずです。実際にカメラを回してみて、あるいは役者にセリフをしゃべってもらってみて初めて「こうした方がいいな」という改善点が見えてくることがあるであろうからです。
特に、シリーズドラマは途中で打ち切りになるかもしれない中での制作ですから、シリーズを完結させるという最終目標とは別に、一話ごとにきちんと盛り上がるポイントをつくり、次回も引き続き観てもらうという中間目標が立ち現れます。
映画作品としては「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」、「スター・トレック」、「ミッション・インポッシブルIII」などを、シリーズドラマとしては「LOST」、「FRINGE/フリンジ」、「パーソン・オブ・インタレスト」などを監督した J・J・エイブラムスはインタビューで次のように答えています。
» 『FRINGE/フリンジ』 あのJ・J・エイブラムスに尾崎英二郎がインタビュー!
インタビュアー:『FRINGE/フリンジ』は、シーズン1より、むしろシーズン2でさらに多くのことが語られ、盛り上がりを見せますね。これは意図的だったのですか?
エイブラムス:『FRINGE/フリンジ』の物語というのは、ここへ来て、僕らが本来求めていたリズムになってきたと思う。
キャラクターの関係性や新事実などが生まれ、物語がだんだんと盛り上がってきたと感じられるのは、それを築き上げてきたからなんだ。一番の盛り上がりから物語をスタートさせようとしても、必ずしもそうは作れない。
どんな物語にも、始まりと終わりがあるよね、”第2幕”というのは何かのターニングポイントであったり、何かが発覚するような出来事が起きたりする。
それが今、僕らの立っているところさ。というわけで、「盛り上がり」というものは周到では用意しきれないようです。
引き続き同記事より。
インタビュアー:ストーリーは、どのくらい先まで考えられているものなのですか?
エイブラムス:沢山考えて準備しているね。しかし、ショウを作っているときには方法論がある。
それはね、物語が進む毎に僕らは何かを学ぶ、ということさ。ショウにとって何が必要で、何が適し、何が適さないかがその行程で判ってくる。そういう意味では、どこに辿り着くかというのは、完全には予測はできないんだ。
考えもつかなかったアイデアが、突如として湧くこともあるからね。
キャラクターがどう機能していくかということもその1つさ。
まさに、文章はキャラクターであり、書き手は監督ですね。
最後に
今回は構成案をきっちり作らずに、
- 「書く前に考えたことしか書けない文章は失敗である」という一文にとにかく感銘を受けたので
- 自分を含め文章を書いている人にはきっと何か感じるところがあるはずなので
- そのあたりを伝えたい
- 何をどう伝えるかはハッキリとは決めていないけど
という状態からいきなり書き始めたのですが、たまたまですが、けっこうスムーズに書くことができました。
役者と監督の喩えを思いついたあたりからの展開は自分としても「おお!」と興奮しましたものの、「いや、すでに過去に記事として書き終えてたし」という“セルフ二番煎じ”を喫したことで、プラスマイナスゼロではありますが…。
というわけで、いますぐ書く気にさせてもらえる一冊です。




