
photo credit: Le Consul via photopin cc
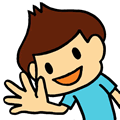 たまたま“発掘”した古い雑誌記事に興味深い内容が書かれていたので、ご紹介。
たまたま“発掘”した古い雑誌記事に興味深い内容が書かれていたので、ご紹介。
いたずらに新たなものばかりを取り入れていてはダメになる。鉛筆作りを存続させることを第一に考えれば、何とかして今あるものを発展させるしかなかった。
「足下を掘るしかなかったと言えばそれまでなんです。だけど、大切なのはそこから何ができるかと考え続けることです」─杉谷和俊(北星鉛筆株式会社・社長)
日経ビジネスアソシエ・2006年9月19日号インタビューより
何か新しいことを始める時、いま自分が持っている、これまでの経験で得られた何かをベースにしなければ、新しい分野にひしめいている先達に勝てる見込みは少ないでしょう。
杉谷氏は、鉛筆を作るときに廃材として出るおがくずを再利用して粘土を作り、「もくねんさん」として商品化します。
鉛筆製造工程では、40%がおがくずとして毎日排出されています。この産業廃棄物のおがくずを資源として無駄なく活用するため、循環型鉛筆産業システムの構築を目標に平成12年より研究を進めてまいりました。
その成果として、おが屑の再商品化事業に成功するとともに、『中小企業創造活動促進法』の認定を受け、木の限りない有効利用とリサイクルに新たな道を開拓しました。
最初はおがくずを固めて薪を作ったそうですが、
- 薪は(既存の)文具の流通ルートに乗せられない
- 薪は夏以外にはほとんど売れない季節商品である
という2つを現実を前にオフシーズンの在庫負担がネックとなって1年で断念。その後、鉛筆と同じ流通ルートに乗り、一年を通してニーズの途切れない粘土に到達します。
ここから得られる教訓は、自分(たち)だからできることを、新たな分野でどう活かせるかを考える、というところでしょうか。
知識としての教訓をどれだけ集めても、日々の仕事には役に立たない
ところで、鉛筆から粘土の話を読んで、『スウェーデン式アイデア・ブック』という本に次のような事例が紹介されていたのを思い出しました。
パイナップルの薄切りがスライス・パイナップルとして売り出された当初、形が揃っていないものや大きさが違うものは全部捨てられていました。しばらく経ってから、だれかが処分するパイナップル片を細かく砕いて、「クラッシュ済み」として売ることを思いつきました。残り物からヒット商品が誕生したのです。
おがくずを再利用して粘土を作った北星鉛筆社長の杉谷和俊氏は、創業者である祖父から以下のようなことを言われていたとか。
「鉛筆のある限り、家業として続けるように」
以下は、杉谷氏が紹介されていた記事の一節。
北星鉛筆は氷河期を生き延びた小動物のごとく、厳しい環境に適応しつつある。これは企業でも、個人でも、ビジネスの世界で生き残るために求められる姿勢の1つだ。先祖代々受け継がれてきた「仕事の哲学」が、杉谷の強さと柔軟性の背景にある。
これに続く形で上記の祖父の言葉が紹介されているのですが、ここで感じるのは、おがくずのような「残り物」を再利用するという発想の原点には、何かしらの哲学があるということです。
おがくずにしてもパイナップルにしても、客観的には「残り物を再利用すればいい」という表面的な教訓にしか見えてきませんが、当事者としては「哲学」があって初めてこの教訓が生かされています。
逆に言えば、「残り物を再利用すればいい」といった知識としての教訓がいくらあっても、日々の仕事にはあまり役に立たない、と思うのです。
冒頭の粘土のエピソードにもあったように、「自分(たち)だからできること」にフォーカスして、改めて考えてみることが突破口になるでしょう。
個人の目線で考えれば、自分のこれまでをつぶさにふり返り、その原点に目を向けることとそのための記録を残していくことがこれに当たります。
地味ですし、効果はすぐには見えないかもしれませんが、自信と手応えをもってやり続けられるテーマを見つける上では、この記録とふり返りのプロセスは欠かせません。
ふり返りの中で見つかるものは、たとえば、
- 何を優先し何を劣後するかの価値観
- 素早く判断を下すための経験に基づいた具体的な基準
- 誰が何と言おうと自分はこうする、というこだわり
といった指標です。これらの指標にはすべて背景があり、理由があり、それゆえに「よりどころ」になります。このよりどころこそが「哲学」と呼ばれるものの実体なのではないか、と僕は考えています。
記録のエッセンスが「哲学」になるわけです。
合わせて読みたい:
さまざまなアイデアの事例が紹介されています。そのうえで、読者に「あなたならどうしますか?」と問いかけてきます。読むというより、考えを進めるための一冊。



