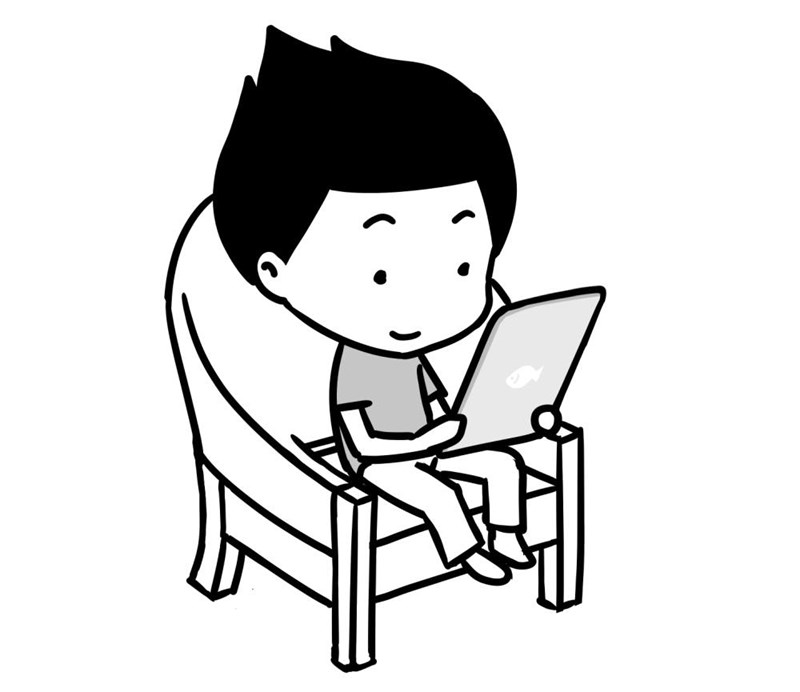『人はいかに学ぶか』
本書は伝統的な学習観を転倒させます。ここで言う伝統的な学習観の特徴は、学び手をどう想定しているかにあります。
伝統的な学習観に特徴的なのは、学び手が受動的な存在であり、しかも有能でないという仮定をおいていることである。
「受動的な存在」とは、教えられたことしか学ばない、言われたことしかやらないといった態度を持つ存在のことです。著者らに言わせれば、この仮定は「人間はなにか不都合がないかぎり非活動的だ」という人間怠け者説を引きずっています。実際は、人間は好奇心があり、不都合がなくても積極的に環境と交渉しようとします。「怠け者」ではないわけです。
また、「有能でない」というのは、たとえ積極的に知識を構成しようとしたとしても、それを適切にはなしえない、という見方のことです。そうなると、教える人の存在がきわめて重要になってきます。学び手が有能でなければないほど、教え手の有用性こそが学びの必須要素となってしまうのです。もちろん、教え手の有用性がないわけではないですが、もしそうならならあらゆる独学は失敗してしまうでしょう。「学び手が有能でない」という話も、どうにも怪しそうです。
では、もしこの伝統的な学習観の仮定が間違っているとしたらどうなるでしょうか。
- 学び手が能動的であるなら、単に教えられた知識、伝達された知識を吸収しようするにとどまらず、みずから知識を構成しようとする
- 学び手が有能であるなら、みずからの経験にもとづいて、効果的な環境への働きかけ方、なぜそれがうまくいくのかなど、知識の中核部分をみずから適切に構成することができる
このような仮定をおいて学習を考えていくのが、著者らが呼ぶ「もうひとつの学習観」、あるいは「新しい学習観」です。本書は伝統的な学習観が持つ問題点を指摘し、その上で「もうひとつの学習観」を提示していきます。
「知的生産の技術書」という観点で本書の重要な箇所を挙げるとしたら、以下の部分でしょう。
知識は構成されるのではなくて伝達されると考えるとすれば、良い教師が行うべきことは、できるだけたくさんの知識を伝達することだということになる。もちろん教えたことがある人なら誰でも、伝達さえすればそれが摂取されるとは信じないであろう。けれども、伝達しなければ獲得される可能性はないのだから、できるだけ多く教えたほうがよいということになるのは当然だ。
したがって、教室のなかであれ、またそれ以外の場所であれ、教え手がなすべき第一の仕事は、より多くの知識の伝達ということになっていくであろう。このもたらすところは、学び手の意欲の衰え、いっそうの能動性の低下であることは、われわれが不幸にも現在経験しつつある通りなのである。
つまり、学び手が受動的であり、有能ではないと仮定して学習環境を構築すると、たしかにその通りに学び手が適応してしまう、ということです。この指摘は、知的生産の技術書の読み手としても、書き手としても示唆に富むものです。
『学びとは何か』
本書は、古い知識感を転倒させます。ここで言う「古い知識観知識」は、知識を一つのアイテムのように考えて、それをどんどん増やしていく、という観点です。著者はそれをメタファーをうまく使って、「ドネルケバブ・モデル」として説明します。「ドネルケバブ」で検索してもらえばわかりますが、棒のまわりにお肉をどんどん貼りつけていくイメージです。線形な単純増加が、そこでは期待できます。
一方で本書が提示する知識感は、「生きた知識」です。
最も役に立つ「生きた知識」とは、知識の断片的な要素がぺたぺた塗り重ねられて膨張していくものではない。常にダイナミックに変動していくシステムなのである。このシステムは、要素が加わることによって絶え間なく編み直され、変化していく「生き物」のような存在なのだ。
知識とは「システム」であり、しかもダイナミズムを持ったネットワークであると、本書では示されます。「学び」とはそのネットワークを変化させる行為であり、逆に言えばそれを変化させないものは「学び」ではなく、暗記といった行為に留まってしまうわけです。
よって、知識を役立たせるためには、それを単独的・独立的なものとして頭にたたき込むのではなく、それを「自分の知識ネットワーク」にいかに加えるかが重要となります。自分の内側に、その知識の「居場所」を定めることが大切なのです。
これを理解すると、本の読み方はずいぶん変わってくるでしょう。もちろん、それは能動的で有能な読み方であることは言うまでもありません。
▼倉下忠憲:
新しい時代に向けて「知的生産」を見つめ直す。R-style主宰。メルマガ毎週月曜配信中。