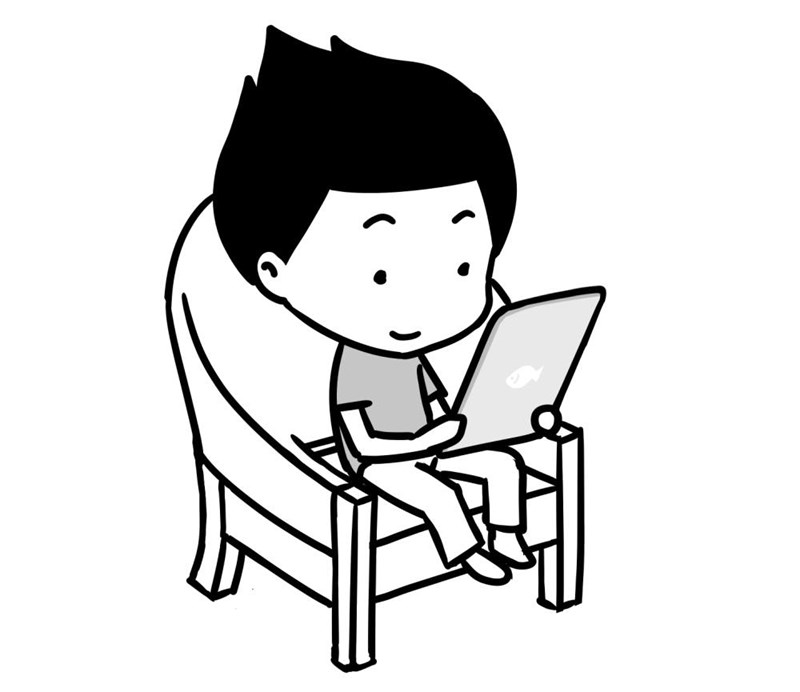『読書論』(小泉信三)
初版が1950年なので、かなり古い本です。一方で、現代でも十分通用する「読書術」が展開されています。
とは言え、多少文章は古いので、重要な部分を箇条書きで列挙しておきましょう。
- 読書の計画を立て、そこにできるだけ古典をいれる
- すぐに役立つものは、すぐに役立たなくなると知る
- 難しい本でも最後まで読み通し、再三読む
- 読んだら本の感想を書く
- ものを見たら本で学び、本で知ったらものを見る
- 読書と読書の間に、読んだことについて考える習慣を身につける
具体的には直接本書を参照してください。簡単に言えば、難しい本であっても身構えず、わからない部分は保留にしておきながら最後まで読む。そういう読書を何度も繰り返していく。その読書の間に、感想を書いたり、内容について考えたりする。といったことを行う、非常にベーシックな読書術です。
『本はどう読むか』(清水幾太郎)
こちらは初版が1972年なのでもう少し現代に近いですが、それでもやっぱりずいぶん昔の感じがします。しかし、本書では「マスメディア」と読書の関係も論じられており(6章「マスコミ時代の読書」)、大きな枠組みとして現代の読書と基盤を共有していると言えるでしょう。
本書では、読書に関するさまざまな論考が展開されていて、読み物としても面白く読めます。仮にその全体のテーマを概略すれば「変化する読書」となるでしょうか。
本を読むことで自分の関心が変化していく、動機付けが変化していく、書物の位置づけが変化していく、読書ノートの取り方が変化していく。
そんな風に読書を通したさまざまな変化が語られています。言い換えれば、瞬間で切り取るのではなく、時間の厚みを持ったノウハウが語られているのです。
そうしたノウハウの中で、重要なものを四つ挙げておきましょう。
その1「なぜ本を読むか」
著者は本を読む理由を簡潔に述べています。
読書というのは、面白い本を読むということである。私は、面白くない本を我慢して読む習慣をまったく持っていない。
なぜか。
しかし、どれだけ高尚な本でも、読者の心の歯車と噛み合わなければ面白くはないし、面白くない本が人間の成長を助けることはない。
ある種の「快楽主義」のような姿勢がここでは提示されています。でもって、これはまったくの真実でしょう。「面白くない本が人間の成長を助けることはない」。おそらくは間違いありません。一方で、読書の先に「人間の成長」がほのかに目指されていることもうかがえます。
その2「書物の三つの分類」
本書では書物を大きく三つに分類しています。実用書、娯楽書、教養書の三つです。それぞれ「生活が強制する本」、「生活から連れ出す本」、「生活を高める本」とその役割が定義されています。面白いのは、同じ本であっても、人によって(あるいはそれを読む目的によって)この分類が変わってくることです。つまり、一般の人にとっては教養書であっても、その分野を研究する学者にとっては実用書(生活が強制する本)であったりする、ということです。
この三つの分類で注目したいのが、独特の存在感を持つ教養書です。教養書は、読むための動機づけを持ちません。それは生活が強制する本でもなく、生活からの逃避として読む本でもないのです。読む必然性が、そこにない。にも関わらず読む本。言い換えれば、教養を磨く(≒生活を高める)ことは、意識的に行わない限り、実行されないのです。
だからこそ、読む本は面白くなければならないのでしょう。本を読むことそれ自身が動機づけになってくれるからこそ、教養本を読むことができるようになるのです。
その3「客観主義から主観主義への読書ノート」
これは読書ノートやメモを書く人には重要な指針となります。客観的に、ないしは著者が想定する文脈において読書ノートを取ることは、そこにある本の「ミニチュア」を作ることに相当します。そうした読書ノートは、自分の関心事、研究テーマを育ててくれません。
むしろ、自分の関心事や研究テーマを中心にして、それに関係あることをピックアップし、それ以外は捨て去るような主観主義の読書ノートが研究を前に進めるのに役立ったと著者は述べています。
一方で、著者は客観主義の読書ノートをまったく否定しているわけではありません。むしろ、読書のスタートアップ期にまず主観主義で読書ノートを取っていたからこそ、その後で自分なりの関心を見つけることができたのではないかと慎重に述べています。これもおそらくはその通りでしょう。
ようするに、読書ノートの取り方も読書経験と共に変化していくものなのです。こうした点からも、「この読書ノート術があれば他は何もいらない」のような言説がいかに危ういかが見て取れます。
その4「思想をテストする場所」
本書の中で、私が一番大切だと思ったのが(主観主義ですね)、以下の部分です。長くなりますが、全文引用してみます。
しかし、私は以前から考えているのだが、思想というものを最終的にテストするのは、家庭という平凡な場所であると思う。活字の世界に生きるだけの純粋思想なら、いくらでも急進的になれるし、いくらでも破壊的になれる。けれども、それが本当に社会を改変する力を持つためには、それが家庭という場所へ入り込み、そこに腰を据えなければならない。
私は日常的に目にする「思想」を試験する際に、この考え方を用いています。「活字の世界に生きるだけの純粋思想なら、いくらでも急進的になれるし、いくらでも破壊的になれる」。それらは奇抜で、恰好良く、得難い存在感を保っているのかもしれないが、しかしそれははたして「家庭」に入り込み、そこに腰を据えることができるだろうか。そんな風に考えるようにしているのです。
私自身に関しても、「理論だけはご立派で、華々しい装いだが、しかし継続的に実践されるものではない」というようなノウハウをばらまかないように注意しています。
▼倉下忠憲:
新しい時代に向けて「知的生産」を見つめ直す。R-style主宰。メルマガ毎週月曜配信中。